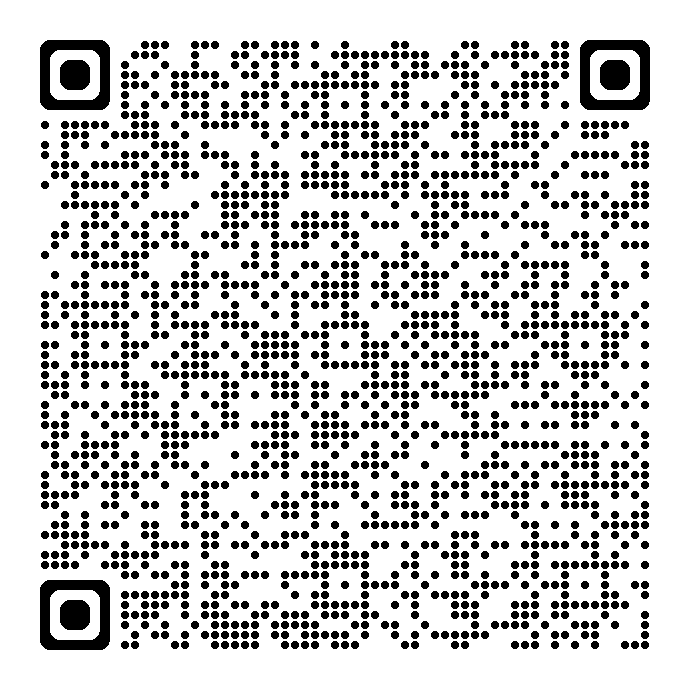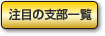隔月で開催している長崎、佐賀合同の指導者講習会7月度を7月6日大村市武道館で行いました。今回は地元講師による講習会ということで、代表の坂口勝浩先生による鎮魂行のあと、午前中は学科の学習、午後は体を動かしての熱い一日となりました。学科では、「修練」「練習」「稽古」「訓練」「修行」の違いや少林寺拳法の目的などを考えました。技術修練では、栗林伴式先生による基本演練のあと、資格によるクラスに分かれてそれぞれの技術修練を行いました。飯塚久雄先生に巡回指導を行っていただきました。その後、坂口先生による指導の下、ローテーションして相手をどんどん変えながら基本的な技について左右均等に技術修練を行いました。エアコンもない7月の非常に暑い武道館において、扇風機と窓からの風だけを頼りに、朝から夕方まで汗びっしょりになって長崎・佐賀、男女、親子、年齢、段位に関係なく、参加した拳士全員が熱心に取り組んでいました。なんて熱心なんだろうと感心いたしました。次回、9月は熱中症対策として、ぜひ涼しい会場で行いましょう。
|
|
 |  |
 |  |
 |  |
 |  |
 |  |
 |  |
 |  |
 |  |
 |  |
 |  |