2023年8月27日(日)大村市武道館において東京八王子富士道院長中島正樹先生を講師にお迎えし約50名の受講者が教えと易筋行を汗びっしょりになりながらも和気あいあいと取り組んだ。法階講義では中島先生が「金剛禅総本山少林寺開創の動機と目的」について講義された。 開祖の体験から「帰国してみると多くの青少年は希望も夢も失い」という部分が今の時代は当時と比べてはるかに豊かにはなったけれど共通しているのは「自分を見失っている」ということに触れられ、「自分が気づいていない」、「自分がいいと思っている事を人に押し付ける」それをお互いが共有していると勘違いしていることにさえ気づいていない。


Z世代の皆さんがこれからの少林寺拳法を支える。自分の言葉で教範や副読本から学んだ言葉でなく、行動で日常に活かすこという事を忘れないようにしてほしい。そして「開創の動機と目的」に共感できる。なぜですか?、どこに共感しますか?、本当はお聞きしたい。そうすると開祖の教えは生きてきます。自分の行動につながります。開祖の経験された事に自分の経験をプラスして「開創の動機と目的を理解してほしい」少林寺拳法用語でない言葉で話が出来るよう「創造」してほしい「技」で終わるのではなく「価値の創造」をしてほしい。金剛禅は「禅」ですから自分の言葉を使って自分らしく「創造」してほしい。と最後に「付箋」を全員に渡されて質問は「少林寺拳法が今の時代の必要感って何ですか?自分の経験、言葉で書いて下さい。指導していて役立った事も書いて下さい」と説明があり、「書いた人は黒板に貼ってください」と、書いた人が次々と貼っていくと、「では時間が少ないですが読んで行きます」と「少林寺拳法の大会ではみんなスターです」「命」「あなたの演武もすごいけど、あなたを応援するのが楽しい」「人とはどうあるべきか考えることが出来る」「練習に来てよかった」「仲間作りと技の魅力」次々に読み上げられた。講習会を通じて「少林寺開創の動機と目的」を試験のために暗記したりした人は多いと思うが、具体的に一人ひとりの心に訴えられた講習会は考えさせられた。
講義前の70分間は易筋行を中島正樹先生が指導された。



僧階講義②は飯塚久雄講師(島原城南道院長)テーマは宗論(宗教論)6宗教概論B5 「宗教はいかにあるべきか」
『教範』に述べられた開祖の宗教観をもとに、現代における主教と人々の信仰のあるべき姿について講義が行われた。冒頭では、社会的信用を失くしている日本の宗教の現状「オウム真理教」や「旧統一教会」問題などを話された。宗教と聞いただけで敬遠する人が多いが外国では無宗教は野蛮人とみられる。
なぜ、宗教はあるのか、何を宗教というのかについては教範に述べられている開祖の宗教観について説明があり、「正しい宗教とは」釈尊の教えは、不養生をして病気になったのを癒してもらうように願う教えでなく、無駄使いをしたあげく、借金が出来て苦しい時にお金が儲かるように祈る教えでもない。不幸や災難をなくしてもらう教えではなくて、不幸や災難を苦にする心を省みてその不幸に打ち勝つ力を得さしてもらう教えである。総て無反省に我利や利己を中心として都合の好いように願う宗教では断じてないのである。釈尊の教えは自己を反省することに始まる。と読み講習をされた。

そして、釈尊の教えから逸脱した現今の仏教の現状を列記して、正しい宗教の在り方を
1,生身の生き方を問い続けること。
2,呪術や祈祷に頼らず、教えに依ること。
3,この世に理想境を打ち建てるため、社会に貢献すること。
4,苦行でなく、養行に精進すること。
5,教えを日常生活の中で実践すること。
6,職業生活を含めて、普通の社会生活を送ること。これらの諸点こそ、釈尊の《正しい》教えと金剛禅の接点なのです。
仏教は智慧と慈悲の獲得・実践を目指す宗教 仏教の悟りの本質は「智慧」と「慈悲」
慈悲について「いつくしみ」「あわれみ」の意味であり、「慈」と「悲」とはもともとは別の語である。「慈」とはサンスクリット語のmaitri (マイトリー)という語の訳である。「真実の友情、純粋の親愛の念」を意味する。これに対して「悲」とはサンスクリット語のkarunaの訳で「哀憐」「同情」「やさしさ」「あわれみ」「なさけ」を意味する。(引用 慈悲中村元著) 父は、子どもが元気がないときに「頑張れ」「クヨクヨするな」と励ましの言葉を掛ける。 母は、子どもがつらそうにしている時にそっとそばに来て、何も言わずに「つらいね」とそばに寄り添う。
小林一茶と橘の伊南(良寛の父)慈悲は実感がこもる。一茶が詠んだのは「やれうつな ハエが手をする 足をする」そして橘以南は、「そこ踏むな 夕べ ホタルがいたあたり」一茶は思わず、参りましたと頭を下げた。以南の句では、どこも踏めないことになってしまう。(引用:玄侑宗久ブログ) 最後に金剛禅の修行法を自分の生活の中で実践している内容を具体的に伝えられた。
<信仰の確立>ダーマ信仰の確立を指しますが、自分が生きていく上で大事な信念を確立する。
<調息・坐禅>調息・坐禅を通して自律神経を整え、集中力、平常心を身につける。
<問法修学>教範学習を指します。※教範とは金剛禅のいわゆる教科書です。金剛禅に関わらず怠らず学びつづける。読書は最適です。
<反省行>日々を振り返り、日記などを付けてその日を省みることです。反省の上に立ち、未来に向けて成長します。
<感謝行>自分に与えられた全てに対して感謝の気持ちを持つことです。
<持戒行>自分を制御するための行です。タバコは「開祖が一つぐらい持戒しろ」と言われ本山で仲間と一緒の講習会で止めました。
<易筋行> 少林寺拳法によって心身共に逞しくなります。
<整体行>身体を整え、健康を維持するために施す身体調整法のことです。 定期的にケアに行っている。島原城南道院ではウオーミングの時に二人組になり拳士同士で行っています。
<托鉢行>社会に対する奉仕のことです。拳士会では数年前から本山が災害が起きた時だけでなく、災害基金を受け付けられた時から毎年1月にわずかですが送金しています。私は赤十字などに毎月すこしだけ寄付を行っています。確定申告で減税になりますがそれは目的ではありません。卒業した学校にも年末に毎年備品などを購入してもらうようにわずかな寄付をしている。(無財の七施)は誰でもすぐにでも出来るので道院で実践するといいでしょう。
<休養> 好きな趣味に没頭するとか、体を休めることです。
<食養>食物を感謝を込めて頂く事です。バランスのよい食事は健康を保つ大事な要素です。毎朝リンゴをすりおろしてガーゼで絞ったジュースを飲んでいます。腸が弱かったけど驚くほどの効果があります。 <排泄>体に毒素をため込まない事です。休養、食養、排泄のサイクルが大事です。
長崎県教区長 法座道院長プログラム あうんVol82「金剛禅教団の理念」の制定

1 はじめに
金剛禅教団では、このたび、「金剛禅教団の理念」を制定しましたが、これは、一つ の組織体として社会の中で存在し、永続的に永続的に活動していくための「最上位の目 的」です。この理念は、金剛禅教団の様々な諸活動をすべて束ねる目的の中の目的です。 そこで、周知徹底を図る意味からも、今一度、その内容についてお話しします。
2 制定の背景
金剛禅には、ダーマ信仰という確固たる教義が存在します。人間は、大宇宙の大霊力 ダーマの分霊として存在し、その分霊たる霊魂を所有しています。そして、霊魂とその 住家である肉体を修養することで、真に己を拠り所とし、世のため人のために役立つ人 間になることを目指す。これが教義の根本です。
金剛禅門信徒にとっては、教義が修行の背骨です。その一方で、教団という一つの組 織体が活動を展開するにあたっての背骨となるのが、「金剛禅教団の理念」なのです。3 「金剛禅教団の理念」の解説
「金剛禅教団の理念」の冒頭には、
① 全門信徒・道院長・役職員が、自己の人格を磨きこれを高める。
私たちは修行をすることを旨とした団体であることから、自己の人格、霊魂を修養 していくことが出発点であり、それにより正しい判断力や決断力、行動力を体得して いきます。
② 幸福を追求する。
「幸せ」とか、「生きがい」というものは、つまるところ、開祖が述べられている ように人間関係の豊かさに価値を感じることにより、真に幸せな世界が可能になると いうことです。
③ 金剛禅の価値を創造する。
開祖は、少林寺拳法を「身心一如・自他共楽のあたらしい道」と示されました。し かし、たとえ当時は真新しかったものでも、それを刷新していかなければ古びたもの となってしまいます。さらに進化させレベルを高めるために常にその価値を創造して いくことが求められています。つまり、少林寺拳法に内在する「宝」を現代に適した 形で創造していく必要があります。
と示されています。
4 具体的三項目
今回定められた「金剛禅教団の理念」では、更に三つの小項目を付加されています。 ① 人間本来の使命を自覚し、たゆまず自己変革し続ける人をつくる(信条)。
② 社会変革に果敢に取り組む、志あるリーダーをつくる(開祖の志)。
③ 金剛禅運動(幸福運動)を先導する、優れた道院長をつくる(活動重点)。
5 終わりに
「金剛禅教団の理念」では、まず「幹」として「全門信徒・道院長・役職員が、自己 の人格を磨きこれを高め、幸福を追求するとともに、金剛禅の価値を創造し、物心両面 において調和のとれた、平和で豊かな社会づくりに貢献する。」と定め、さらにその細 目として三項目が定められています。教団の理念を自らの肚に落とし込んだ上で、ゆる ぎない信念を持って、金剛禅運動に取り組んで参りましょう。
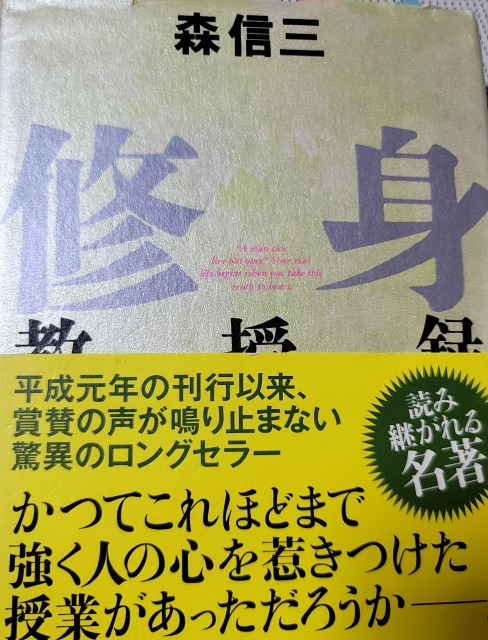

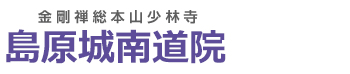

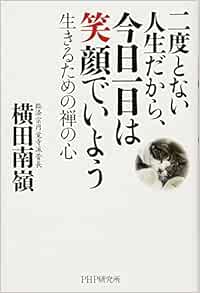
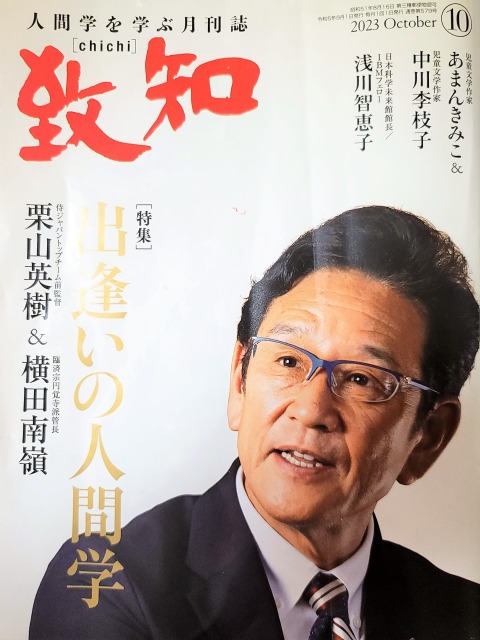










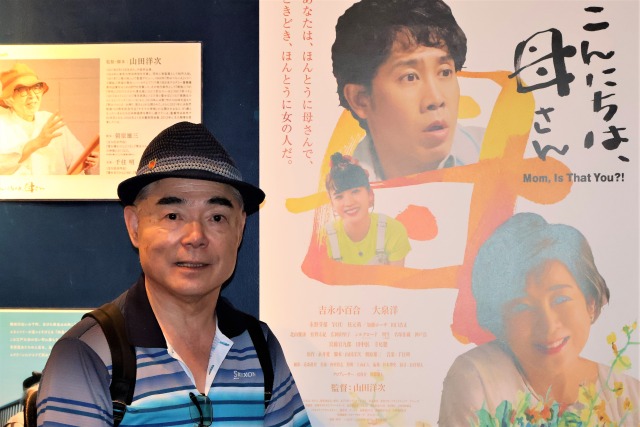 2
2












